産後うつ予防にもつながるスウェーデンの産後ケア|0〜5歳の子ども・ママ・パパを支える北欧子育て支援のしくみと実例
無料健診・予防接種・家庭訪問・発達支援と父親の育児参画までを解説
- 長谷川佑子(はせがわ・ゆうこ/Yuko Elg)
- Glolea! スウェーデン子育てアンバサダー
北欧スウェーデンの産後ケア・母子保健は、地域のプライマリ・ケア併設の子どもケアセンター(乳幼児健診センター/BVC[Barnavårdscentralen]) が中核となっています。多くの家庭が地域医療を選び、乳幼児健診センターの看護師が出生直後〜就学前(0歳〜5歳)まで継続支援が行われます。家庭訪問・定期健診・予防接種・育児相談が無料で提供され、必要に応じて保育所や関係機関と連携。本記事では、実習と子育ての実体験をもとに、早期退院後の在宅支援/家庭訪問〜健診の流れ/多職種連携/予防接種の進め方/多言語下の言語発達支援/5歳健診から小学校への情報連携まで、家族中心の仕組みを要点解説します。
こんにちは! スウェーデン女王認定 認知症専門看護師/Glolea! スウェーデン子育てアンバサダー長谷川佑子です。

▲子ども一人ひとりに担当となるプライマリーナース(日本では発育健診を行う保健師のような看護師)が付くスウェーデン。
地域のクリニック制度を取っているスウェーデン。
誰もが「自分が選んだ家庭医」を地域のクリニックに持っています。
さらに、子ども一人ひとりには、担当となるプライマリーナース(日本では発育健診を行う保健師のような看護師)が付きます。
そのため、クリニックで子どもとその家族は継続的なケアを受けられます。
私は現在、大学院の地域ケア専門看護師コースに在籍しており、子どもケアセンターで実習に参加してきました。
今回の記事では私自身の
- スウェーデンの子どもケアセンターでの実習経験
- スウェーデンでの子育て中に受けてきた支援体験
をもとに、0歳〜5歳(産後から就学前まで)の長期にわたる、スウェーデンの「プライマリーチャイルドケア」についてお伝えできればと思います。

目次
- スウェーデンの産後ケアと母子保健とは? 無料提供される乳児・幼児への支援
- 早期退院が当たり前? スウェーデン流・産後の在宅ケアとは
- 家庭訪問と健診の頻度は? 0〜5歳の子どもに寄り添う看護師のサポートスケジュール
- 困ったときはすぐ相談!柔軟につながることができる地域支援
- 産後クライシスを乗り越える 「産後うつ」のスクリーニングや保護者の不安もケアするスウェーデンの子育て支援
- 子どもの成長は家族と一緒に見守る スウェーデンの伴走型サポート
- 1歳を過ぎたらどうなる? 支援頻度と保育園との情報連携の実際
- 子どもがリラックスできる環境とは? 待ち合いスペースと健診室の工夫
- 健診は“聴く”から始まる…フォローアップ重視の進め方
- 予防接種は“子どもの選択”を大切に 緊張や怖さへの寄り添い方
- 身体測定もコミュニケーションの時間 父親の関わりも自然にサポート
- 肥満を予防するには? 栄養と運動を見守るスウェーデン式アプローチ
- 家庭で話す言葉は? 多言語環境での言語発達をどう支援しているか
- 健診の所要時間は? 約30分の予約枠と“宝箱”のごほうび体験
- 5歳健診の目的とは? 就学前に行う情報共有で担当看護師から“卒業”
- まとめ|母子と家族に寄り添うスウェーデンの子育て支援の本質
- 関連記事|スウェーデンの育児・教育制度と子育て体験談
スウェーデンの産後ケアと母子保健とは? 無料提供される乳児・幼児への支援

スウェーデンの子どもケアセンター(乳幼児健診センター)「Barnavårdscentralen(BVC)」は、子どもの健康と成長を支える重要な地域医療施設です。
産後、病院からの帰宅後およそ1週間で家族はケアセンターを訪れ、担当の地域看護師と0歳〜5歳の就学前まで継続的に面会&支援が行われます。
ここで子どもの発達の様子や健康状態を丁寧に確認していきます。

以下の支援も0歳から5歳まで無料で提供されています。
- 健康管理
- 予防接種
- 育児相談
ケアセンターは地域ごとに設置されており、親はケアセンターや担当看護師を選ぶことができます。
こうした体制により、スウェーデンでは産後の家族に対する早期介入や継続的なサポートが実現されています。
早期退院が当たり前?
スウェーデン流・産後の在宅ケアとは
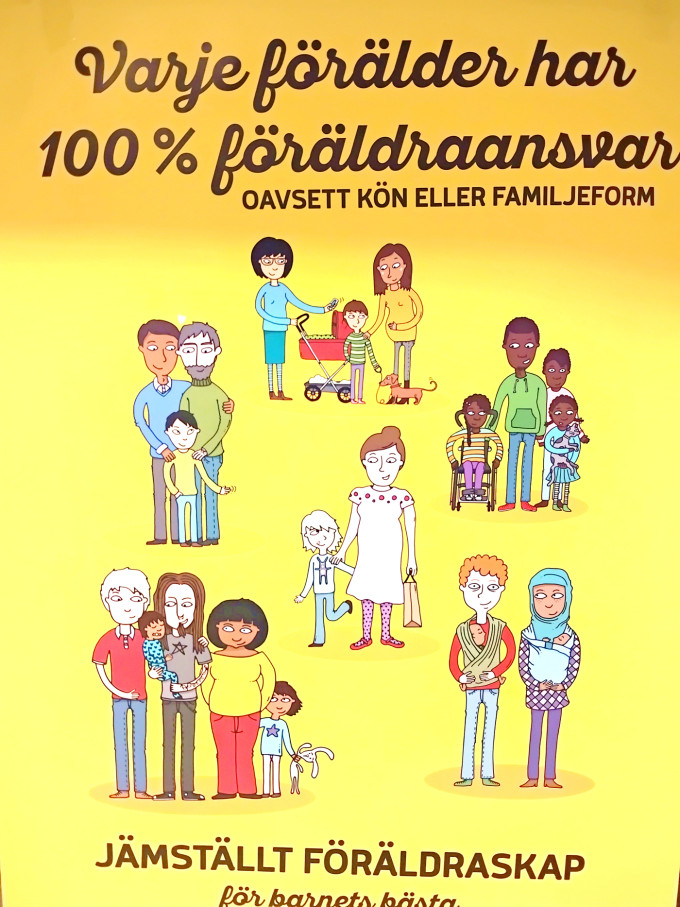
▲「親は100%子どもの責任があります」というメッセージが趣旨のポスターには、スウェーデンらしく様々な家族の形があることが伝わってきます。
スウェーデンでの出産は地域ごとの病院で行われ、パートナーが分娩に付き添うのが一般的です。
産後、母子ともに健康で、子の体重が十分であれば、早い家族では生後6時間で自宅に戻ります。

もし、産後も病院にいる場合は、子どもか母親への医療的ケアが必要なためであり、それ以外のことは基本的に何もしてもらえません。
授乳やケアは親の責任で行います。
つまり、病院にいるからといって育児に関するサービスがあるわけではなく、美味しい食事が出てくることもありません。
多くの家族は、自宅のほうが慣れた環境で育児を始められ、母親もリラックスして休息が取れるため、自宅に戻ったほうが良いと言います。
家庭訪問と健診の頻度は?
0〜5歳の子どもに寄り添う看護師のサポートスケジュール

▲スウェーデンの看護師は、産後の家庭訪問を通じて赤ちゃんの健康状態・家族・お母さんの産後の体調を丁寧に見るていきます。
生後まもなく家族が自宅に戻ると、新生児病棟の助産師が自宅を訪問し、
- 母乳育児の支援
- 母親への産後ケア
を行います。
その後、生後約5日前後で赤ちゃんの家族と地域看護師が対面します。
基本的には看護師が家庭を訪問し、事前に電話で困りごとがないか、自宅での状況を確認します。
この時期は、赤ちゃんの健康状態と家族、特に母親の産後の体調を丁寧に見ていきます。
以降は、一週間に一度、家族が子どもクリニックを訪れて子どもの成長と家族の健康を確認します。
生後一か月を過ぎると訪問頻度は二週間おきに変わり、二カ月以降は月に一回、担当の看護師に会います。
困ったときはすぐ相談!柔軟につながることができる地域支援
基本的には、国の子ども保健事業により、家庭訪問や子どもケアセンターでの支援・健診が実施されます。
ただし、成長が十分でない場合、赤ちゃんの睡眠がうまく取れない場合、子育てへの不安がある場合などは、いつでも担当看護師に電話で連絡でき、必要に応じて面会することもできます。
産後クライシスを乗り越える
「産後うつ」のスクリーニングや保護者の不安もケアするスウェーデンの子育て支援
助産師・医師・カウンセラーなどとのチーム連携で支える子育て

両親に対しては
- 授乳
- 離乳食
- 睡眠
- 発達
に関するアドバイスを提供することはもちろんのこと、育児生活での不安や困難にも対応。
必要に応じて
- 小児科医
- 心理カウンセラー
など専門機関への紹介を行います。
また、産後うつのスクリーニングや家庭の状況把握も行います。
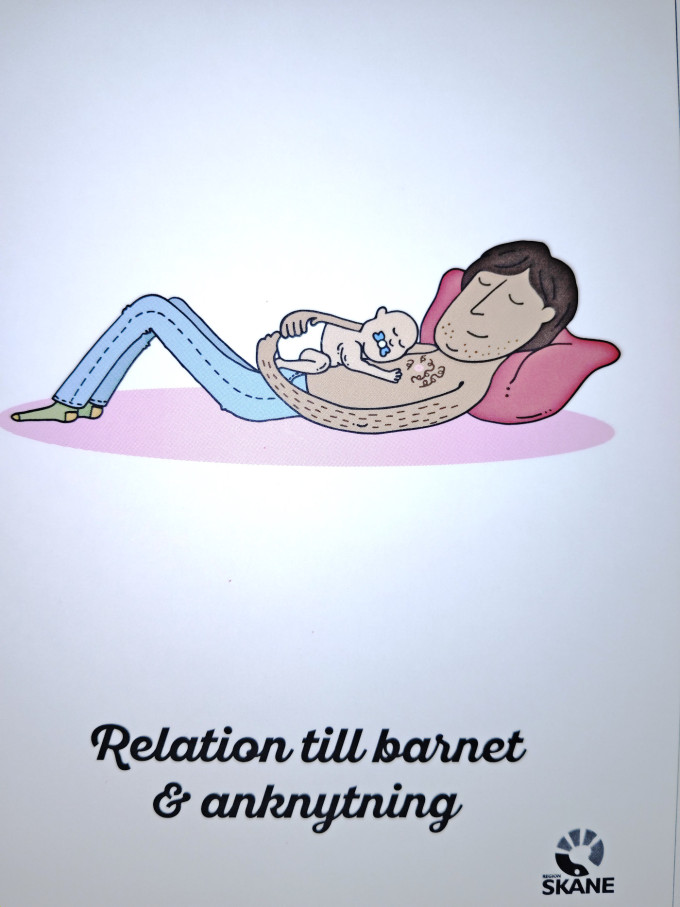
▲スウェーデンの親子の愛着形成を促すポスター
分娩を経験していない親(多くが父親)に対しても、個別に
- 新しい家族を迎えての生活状況
- 仕事と家庭の両立
- 親としての思い
について話しを聞き、支援が必要であれば、ソーシャルワーカーや保育園などと連携し、子どもと家族に総合的なサポートを提供します。
子どもの成長は家族と一緒に見守る
スウェーデンの伴走型サポート

子どもが1歳を超えるまでは、家族は子どもセンターの看護師と頻繁に会い、成長や生活面について継続的な支援を受けます。
一方で、子どもが歩き始め、食べるようになり、保育園に通い始める1歳以降は、訪問の頻度が徐々に減ります。
とはいえ、この時期からは看護師が家族や保育園と密にコミュニケーションを取り、よりよい成長を引き続き支援します。
1歳を過ぎたらどうなる?
支援頻度と保育園との情報連携の実際
支援の頻度は次のとおりです。
- 1〜3歳:半年に一回
- その後(〜5歳):一年に一回
いずれも、同じケアセンターの同じ看護師が担当し、継続性のあるフォローが行われます。
子どもがリラックスできる環境とは?
待ち合いスペースと健診室の工夫

▲子どもがリラックスしやすい環境設定がされている診察前の待合室。
健診を受ける子どもと親は、まず待ち合い所で待機し、予約時間になると看護師が呼びに行きます。
待ち合い所にはおもちゃや本が置かれており、多くの子どもがリラックスできる空間になっています。
そのため、子どもの身体機能の発達や言語の様子は、健診室よりもここで観察したほうが分かりやすい場合もあります。
子どもが遊びに夢中になっているときは、無理に健診を受ける部屋に入ることを急がせません。
子どもの様子を見守りながら、親から普段の生活や様子を聞き取り、保育園の先生が記入した発育の記録も受け取ります。
健診室にもおもちゃや絵本、子ども用の机といすが用意されており、できるだけ子どもがリラックスできる環境づくりがされています。
健診は“聴く”から始まる…フォローアップ重視の進め方

まず、子どもと家族が入室したら
調子はどうですか?
最近はどうでしたか?
といった、家族が“今いちばん話したいこと”から会話を始めます。
そのうえでフォローアップに移り、例として
前回の健診ではお腹の具合があまりよくないと話していましたが、その後どうですか? 赤ちゃんへのお腹マッサージを教えてあげましたが、やってみましたか?
のように、前回の課題と支援策の効果を一緒に確認します。
健診中、子どもが走り回ったり遊び始めたりすることもあります。
なので、家族と子どもの様子に合わせて柔軟に検診を勧めていきますが、まずは「話を聴く」ということを大切にします。
看護師は家族に寄り添い、子どもだけでなく、産後で疲れている母親の体調、10日の出産休暇を終えた父親の仕事と新しい家族生活のバランスにも気を配り、家族みんなの健康を支援します。
予防接種は“子どもの選択”を大切に
緊張や怖さへの寄り添い方

2〜3歳の子どもには、まず今日の健診内容を説明し、予防接種がある場合は写真付きガイドを用いて伝え、何から始めたいかを本人に確認します。
予防接種が予定されている家庭には、事前に健診内容と予防接種についての写真付き案内を送付し、健診前に「何をするのか」を子どもに説明しておくことを勧めています。
ただし、子どもへの説明の仕方は家庭によって大きく異なります。
ある日の健診では、5歳の子どもが家族から事前説明を受けておらず、看護師から予防接種の話をされた途端に表情が硬くなり、おびえて話もできなくなりました。
一方で、準備のよい家庭では
予防接種をがんばれたら帰りにアイスを買って帰ろうね!
などの約束をしており、子どもは注射が嫌でもそれなりの心の準備をして来院します。

予防注射への恐怖心は子どもによって様々です。
看護師は健診時間の中で、
- いつ注射をするか
- 親の膝の上がよいか
などを子どもに確認し、緊張をほぐしつつ『子どもの自己決定』を尊重し、予防接種も健診も行っていきます。
このような医療者の姿勢は、子どもが医療者と対等であると理解し、人生を通じて医療と信頼ある関係を築くうえで、とても重要だと思います。
また、幼い頃から尊厳を大切にした対応を積み重ねることで、高齢者が認知症になってからも、私が医療者だと理解してくれると(わかってもらいやすいように看護師の名札を大きくしたり、必要がない場面でも聴診器で検査する仕草を見せるなどしています)。
その結果、医療者への信頼が保たれ、予防接種を拒否することがほとんどないことにつながっているように思います。
身体測定もコミュニケーションの時間
父親の関わりも自然にサポート

身体測定は、小さな子どもの場合は親が洋服を脱がせます。
健診に父親が同伴している家庭では、ほとんどの場合、父親が子どもの着替えを担当していたのが印象的でした。

どのお父さんも手慣れていて、子どもとのコミュニケーションもとても上手でした。
発育測定後は、発達曲線を家族と一緒に確認し、それぞれの子どもが年齢に合った成長をしていることを説明します。
肥満を予防するには?
栄養と運動を見守るスウェーデン式アプローチ

2歳を過ぎる頃からは、BMIの値も確認します。
体重が少ないことよりも、体重が多いことで将来さまざまな疾患のリスクが高まるため、BMIが高い子どもの家族には、食事量と運動の重要性を伝えることが大切です。
ただし、体重に関する話題をとてもネガティブに受け取る保護者もいるため、まずは保護者の知識や考えを十分に聞き取ることから始め、過度に「指導する」スタンスは取らないようにしています。
家庭で話す言葉は?
多言語環境での言語発達をどう支援しているか
言語発達のスクリーニングでは、自宅でどの言語を使っているか、どんな本をどのくらい読んでいるかといった点を丁寧に聞き取ります。
ほとんどの保育園はスウェーデン語を主言語としていますが、家庭でスウェーデン語以外を使っている子どもでもスウェーデン語を理解できる例は少なくありません。
一方で、多言語を使う子どもの言語発達の評価は難しいとされています。
また、健診という慣れない場では話せない子どももいるため、看護師は保育園と連絡を取り、普段お友達とどのようにコミュニケーションを取っているかなど、日常場面での言語発達の様子を把握します。
発達の遅れが見られる場合には、言語聴覚士によるサポートを受けられるよう、診療依頼を出すこともあります。
健診の所要時間は?
約30分の予約枠と“宝箱”のごほうび体験

身体測定だけの場合は、一人の子どもにつき約30分の予約時間を入れています。
一方、予防接種やその他のスクリーニング検査がある場合、または親の健康状態の聞き取りを行う場合には、1時間の予約時間を取ります。
子どもが健診を終えて帰るときには、看護師の「宝箱」から一つ、自分の気に入ったおもちゃをもらって帰ります。
部屋に入ってきたときは硬かった表情も、おもちゃを選ぶ頃にはキラキラした目に変わり、みんな
またね!
と笑顔で帰っていきます。
5歳健診の目的とは?
就学前に行う情報共有で担当看護師から“卒業”

5歳の健診では、これまでの経過を家族と振り返り、記録を作成し、子どもが通う小学校へ情報を送ります。
この時は、担当看護師からの卒業という雰囲気で、
家族の一番近くにいて子育てを伴走してくれる大きな存在だった
と地域看護師のことを評価する声が多く聞かれます。
まとめ|母子と家族に寄り添うスウェーデンの子育て支援の本質
子どもケアセンター(BVC)の役割とは?|地域看護師が担う日々のサポート

スウェーデンの子どもケアセンターは、乳幼児期の健康と発達を支えるために欠かせない存在です。
ここでは、地域看護師が中心となって子ども一人ひとりの成長を見守り、必要に応じて家族に対する継続的かつ包括的な支援を提供しています。
保護者と信頼関係を築きながら、ただの健康診断にとどまらず、家族全体の安心と福祉にも目を向ける姿勢が特徴です。
看護師が向き合うのは子どもだけじゃない|保護者の声に耳を傾ける医療現場

地域看護師の役割は単に子どもの健康状態をチェックすることだけではありません。
健診の時間には、保護者の不安や悩みにもじっくりと耳を傾け、家庭全体の状況を落ち着いて観察することが重視されており、看護師自身も、
最初から特定の問題に集中しすぎないことが大切
と語り、まずは親子の語るエピソードに関心を持つことの重要性を強調していました。
“ただの健診”だけではない
子どもと保護者に向き合うスウェーデンの温かなケア

子どもケアセンターは、子どもや保護者が健康や成長に関する相談をする最初の場所であり、支援の出発点でもあります。
定期的なモニタリングを通して子どもの発達の進捗を確認し、状況に応じて支援プランを柔軟に調整していきます。
家庭ごとに異なる背景や価値観を尊重しながら、その都度必要なサポートを個別に提供していく姿勢は、スウェーデンの医療福祉のあり方を象徴しているようにも見えます。

看護師は保護者が無理なく実行できるセルフケアの視点を大切にしています。
看護師からのアドバイスが負担とならないよう常にバランスを意識しており、保護者が子育てに責任を持ち、積極的に関わるためには、専門的な知識を一方的に押しつけるのではなく、実際の生活に役立つ情報をわかりやすく伝える工夫をしています。
このように、子どもケアセンターでは子どもを中心に据えながらも、家族全体を支える「個人および家族中心のアプローチ」が実践されています。
保護者がケアの計画やフォローアップに主体的に関われるよう促すと同時に、子どもの視点にも細やかに配慮した支援が行われ、また、他機関との連携が必要な場合には、必ず保護者から書面で同意を得た上で対応するなど、個人の権利とプライバシーを尊重する仕組みもしっかりと整備されています。
子どもと家族に寄り添う存在として子育てを支える“地域のパートナー”という役割を持つスウェーデンの子どもケアセンター

スウェーデンの子どもケアセンターは、単なる医療施設ではなく、子どもとその家族に寄り添い、共に成長を支えるパートナーとしての役割を果たしています。
その丁寧で柔軟な対応からは、子どもを社会全体で支えるという理念が、確かな実践として息づいていることがわかります。
関連記事|スウェーデンの育児・教育制度と子育て体験談

- スウェーデン子育て事情 from Glolea![グローリア]
- 虫歯&歯周病ゼロを目指す!予防歯科先進国「スウェーデン」式の歯磨き&口腔ケアテクニックとは?from Glolea![グローリア]
- スウェーデンで行われている性教育 from Glolea![グローリア]
- Besök på barnavårdscentralen, BVC [from 1177.se]
- Barnavårdscentral[from Wikipedia]
記事をお読み頂きありがとうございました!
みんなの評価: (件)
- 海外移住
- スウェーデン子育て事情
- スウェーデン
- 海外子連れ移住
- 北欧の子育て事情
- 北欧子育て事情
- 北欧の子育て
- 子ども支援
- 北欧の教育
- スウェーデンの産後ケア
- 北欧の産後うつ予防
- 北欧の母子支援制度
- 予防接種 子ども 怖がる
- スウェーデンの父親育児参加
- スウェーデンのチャイルドケア
この記事を執筆したGlolea!アンバサダー
- 長谷川佑子(はせがわ・ゆうこ/Yuko Elg)
- Glolea! スウェーデン子育てアンバサダー
- ウプサラ
2008年からスウェーデン王国、ウプサラで暮らしています。スウェーデン人の夫、3歳の娘の3人家族。森でのベリー摘み、湖での水遊び…日本とはちょっと違った子育てをしつつ、北欧文化を体験する日々です。 母親も外で働くのが当たり前の国での社会のしくみ、女性たちの生き方もお伝えしたいと思います。



 ©tiedhearts, Inc.
©tiedhearts, Inc.